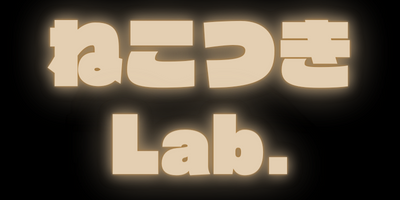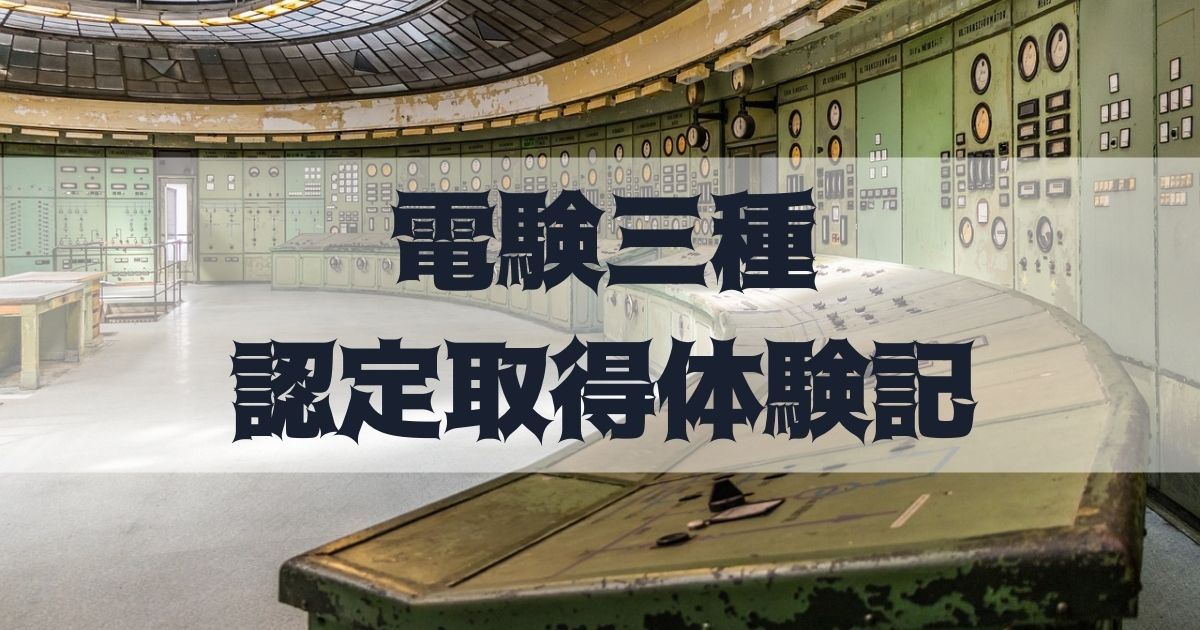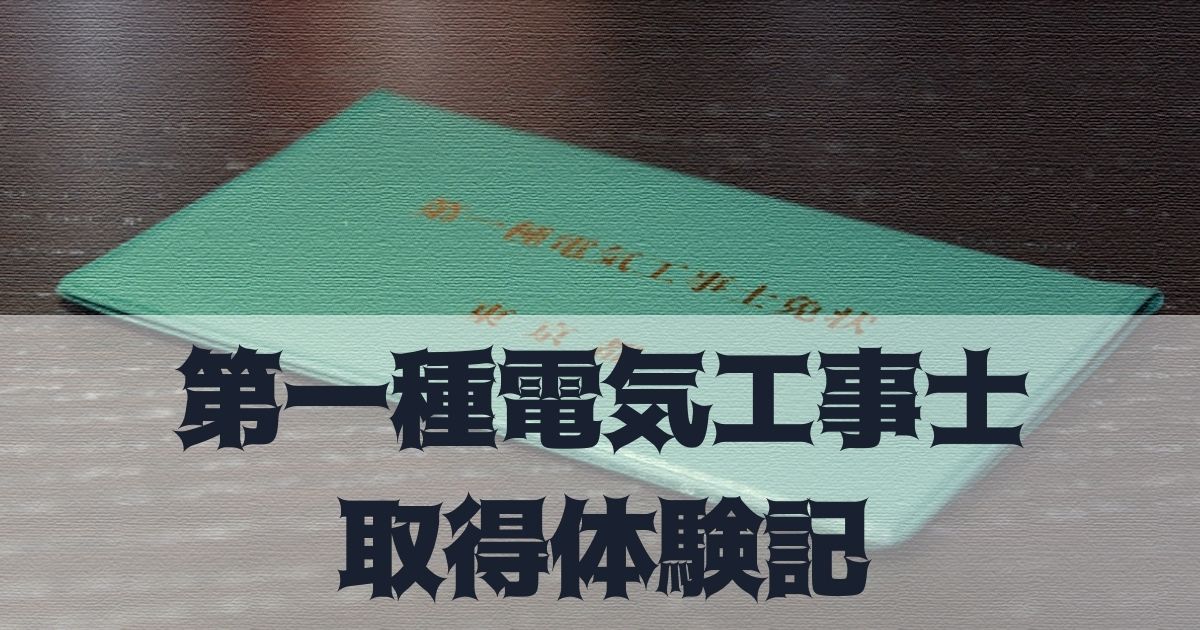ビルメン4点セットとビル管(建築物環境衛生管理技術者)を取得し、ようやく人並みのビルメンになれた私は次の目標に第三種電気主任技術者の認定取得を目指しました。
しかし私の配属されていた現場は、最初は電気主任技術者が常駐していましたが途中で異動になり、電気主任技術者を外部委託することになりました。
電気主任技術者を外部委託していた期間は実務経験になるのか、関東東北産業保安監督部に電話で問い合わせしたところ「実務経験になる」との回答だったので、認定取得に挑戦することにしました。
第三種電気主任技術者を認定で取得した際に、実際に困ったことや解決方法などをまとめましたので、今後認定取得する方の参考になれば幸いです。
第三種電気主任技術者とは
ビルメン業界で3種の神器と呼ばれる難関資格のうちのひとつ、第三種電気主任技術者。
この資格を取得するには試験による合格と認定による取得の2種類の方法があります。
試験による合格は3年以内に「理論・電力・機械・法規」の4科目合格しないといけません。1科目ですら難しいのに4科目、しかも期限付き。
認定による取得は電気系の高校・専門学校・大学を卒業して、さらに一定の実務経験が必要です。私は工業高校の電気科を卒業していたため、第三種電気主任技術者の認定取得が可能でした。
当時は普通科に行きたくないから選んだ電気科でした。卒業後はIT系の専門学校へ進学してIT系の企業に就職したので完全に無駄になったものと思っていました。
それが巡り巡って電気科を卒業していることに助けられることになるとは、人生とはわからないものである。
第三種電気主任技術者認定までのスケジュール
まずは認定取得に向けて、私はインターネットをメインに情報収集しました。他の方の体験記はとても参考になりました。
- 2019年9月初回受付予約の電話
- 2020年1月認定面談(1回目)
実務経歴証明書と必要書類(卒業証明書、単位取得証明書、住民票)のチェック
- 2020年6月認定面談(2回目)
実務経歴証明書のチェック
- 2020年9月認定面談(3回目)
実務経歴証明書のチェック
- 2021年2月認定面談(4回目)
実務経歴証明書のチェック
- 2021年4月実務経歴書証明印の申請
- 2021年5月書類提出
- 2021年8月免状到着
初回受付予約の電話から初回認定面談まで
私は関東東北産業保安監督部で申請しました。ここは初回予約を取るまでに3ヶ月以上待たされると情報があったので、実務経歴証明書を作る前に予約だけ取ってしまうのがいいと思います。
実際に私の予約日も3ヶ月以上先でした。
初回の認定面談までに必要書類を準備します。
単位取得証明書は「電気主任技術者用の単位取得証明書」が必要になります。
卒業校のホームページには「電気主任技術者用の単位取得証明書が必要な場合はお知らせください」とあったので電話して問い合わせてみたのですが、受付事務の方はその存在を知らなかったのです。
とりあえず通常の単位取得証明書を発行してもらいました。当然、後日再提出になるわけですが
ビルメン業界では3種の神器と呼ばれている電気主任技術者も、一般人から見ればこの程度の扱いなのです。
また、主任技術者免状交付申請書に収入印紙を貼るよう記載があったので、とりあえず収入印紙買って持っていったのですがこれは提出時に貼ればいいのでこの時点では買わなくて大丈夫です。認定が受けられなかった場合、無駄になります。
私の配属されている現場では過去に電気主任技術者の認定者がいなかったため、実務経歴証明書を最初から作成する必要があり、とても大変でした。
精神崩壊寸前でなんとか実務経歴証明書を形にして面談日を迎えました。
認定面談(1回目)
面談時間は30分程。他の方の体験記にあったような面接っぽい雰囲気や質問などは一切無く、1対1で必要書類のチェックと実務経歴書の修正でした。
まず単位取得証明書が再提出になりました。受付事務の方が知らなかったという事情を説明したところ電気科の先生に問い合わせしてみてくださいとのことでした。
実務経歴証明書では以下の点を注意・指摘されました。
- 本籍・現住所は住民票の表記と合わせる
- 勤務先・役職・配属先ビル名などは組織図と合わせる
- 点検項目などは「既定値」ではなく具体的な数値を書くこと
- 電気工作物の概要に計器用変成器(変流器(VT)・計器用変圧器(CT)・零相変流器(ZCT)など)も記載する
- 電気工作物の概要で名称は正確に記載する(例:変圧器→乾式変圧器)
- 電気主任技術者を外部委託していた期間は別で記載する
- ビルの所有者の証明印は貰えるのか確認
- その他細かい誤字脱字の修正など
認定面談(2回目)
コロナウイルスの影響で今回から書類を送付して電話面談になりました。
ここで苦戦したのは前回指摘された「電気主任技術者を外部委託していた時期は別で記載する」というところ。これに関してはインターネット上にもほとんど情報がなかったので困りました。そして外部委託していた間、電気設備点検表を提出する必要があるとのこと。それ前回聞いてないんですけど…。
電気主任技術者を外部委託した場合の実務経験について注意点は以下のとおり。
これには非常に困った。なぜならこの現場では日勤のときしか電気室の巡回点検をしていない。基本シフトは日勤・宿直・明け休み・公休なので、単純に計算して実務経験が1/4になる。そうなると実務経験が3年未満になってしまい認定条件を満たさない。
どうやら電気主任技術者は私には早すぎたようだ。救いは無いんですか…。
私は諦めようとした。しかし救いはあったのだ!
このとき私は別の現場に異動しており、その現場には電気主任技術者が常駐していたので新しい現場の書類を作れば実務経験が合計で3年超えることがわかりました。
正直あの実務経歴証明書をもう一冊作るのはかなり心が折れたが背は腹に変えられない…。
認定面談(3回目)
今回も事前に書類を送付して電話面談。
前の現場の電気主任技術者を外部委託していた期間の点検表と、新しい現場の実務経歴証明書をあわせて送付。とりあえず実務経験の期間はクリアしました。
細かい注意・指摘などあり、修正。
認定面談(4回目)
今回も事前に書類を送付して電話面談。最終的に直したものをメールで送付しチェックされました。
認定許可がでたので、袋とじにして勤務先・ビル所有者それぞれの証明印を貰います。
勤務先の証明印は基本的に問題ないと思いますが、ビル所有者の証明印をもらうのは苦戦するかもしれません。私の場合はビル所有者側の担当者と良好な関係を築いている現場だったので問題なく証明印をいただけました。(認定が終わったあとスムーズに証明印貰えるよう1回目の面談後に連絡しておきました)
一応、ビル所有者の判子がもらえない場合は必要書類を揃えることでなんとかなるみたいですがこれらの書類を揃えるのも大変だと思うので判子で済ませたいですね。
[基本事項]
第1~3種電気主任技術者免状(電力安全課技術係)実務経歴証明書記載要領より
1.実務経歴書は、同一勤務先(1社、1団体)について作成し、2以上の勤務先の実務経験を合計しな
ければ、省令で定める条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書が必要となります。
2.委託管理契約に基づく実務経験の場合(ビルメンテナンス会社等に所属している者)は、自社及び契
約会社(設置者)の両者の証明を受けてください。但し、実務経歴期間内全ての契約書、覚書、仕様書
等を添付出来る場合は、自社のみの証明で結構です。
3.工事業者については、工事工程表及び相手方(設置者)の証明書が必要となります。但し、契約書の
写し(設置者からのもの)を添付出来る場合は、相手方の証明は不要です。
4.組織図及び工事工程表を含めて証明者の割印を必要とします。
書類送付~免状到着まで
簡易書留で書類を送付。
約3ヶ月後、無事に免状到着。初回受付予約の電話から1年11ヶ月掛かりました。
届いた電気主任技術者の免状は素人がWordで作ったような感じで笑っちゃいました。あれだけ苦労したのに…。建築物環境衛生管理技術者の免状は賞状みたいに豪華な装飾が施されていたのにね。
まとめ
- 単位取得証明書は電気主任技術者用の様式を用意する。卒業校の受付事務の人がわからない場合は電気科の先生に問い合わせする。
- 収入印紙6600円は最後に申請するときに貼ればいいので認定通るまでは買わなくていい
- 電気主任技術者を外部委託している期間も実務経験になるが以下の条件あり
- 外部委託期間を実務経験として認めるにはその期間の電気設備点検表が必要
- 実際に点検していることを証明するため点検者の名前が記載されている点検表を提出する
- 点検表の書式に決まりはない
- 申請者が実際に点検した日数が20日で実務経験1ヶ月分に換算する
- 現場で過去に認定者がいると楽。逆に現場で初めての認定者だとかなり大変。
- ビル所有者の証明印が必要になるので事前に確認しておく。貰えない場合は実務経歴期間内全ての契約書、覚書き、仕様書等を添付する必要がある。
私の配属された現場では、どちらも過去に電気主任技術者の認定者がいなかったため、実務経歴証明書を最初から作成することになったため非常に苦労しました。
しかも2現場分の実務経歴証明書を作成したため苦労は2倍でした!!

私が認定を受けるときに過去の体験記はすごく助かったので、私も体験記を残すことにしました。この記事で第三種電気主任技術者認定の助けになる人が一人でもいれば嬉しいです。